お相手は早期退職研究所サロン生活設計の部屋担当講師三原ゆきさんです。
\豊かなセカンドライフが実現するサロン/
本記事は、その時のスペースの書き下ろしです。
この度はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございました。
早期退職アドバイザーのみらいのびたです。
お時間になりましたので始めたいと思います。
まずはこのスペースの目的について簡単に紹介させていただきます。
今回のスペースの目的は私の運営するサロン早期退職研究所の告知と、どのようなサロンなのかを直接お話しする目的で開催させていただいています。
早期退職研究所の理念は「人生100年時代を軽やかに居心地の良い場所でお金と健康の心配に無縁な人生の実現を目指す」です。
今月9月1日の朝7時より9月6日23:59まで特別招待スタンダードプランの登録を開放します。
詳しい情報は下記のQRコードから公式ラインを登録してお待ちください。
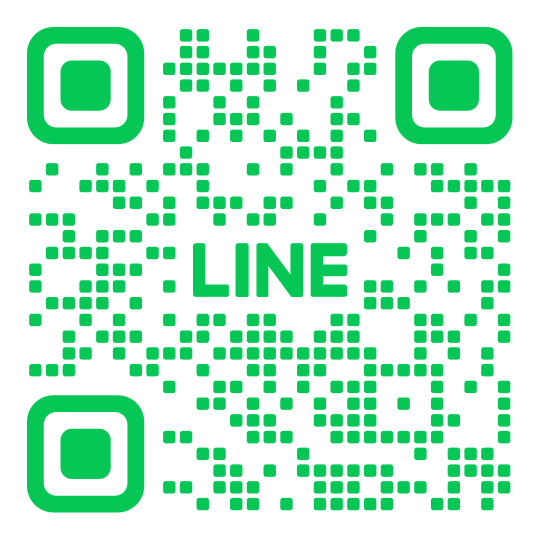
なぜ50代で大学院に? まずはそのきっかけを教えてください。
私は元々、大学院に行きたいというより、「老年学(ジェロントロジー)」を学びたいという気持ちが強かったんです。ファイナンシャルプランナーとして、定年前後の方の相談を数多く受ける中で、お金だけでなく人間関係や健康、介護といった複合的な問題に関わる場面が増えていました。そうした中で、横断的に「老後」を捉えられる知識が欲しいと感じるようになりました。
老年学が学べる教育機関を探していたところ、大学院しか選択肢がなかったんです。それで、桜美林大学大学院の老年学コースに進むことを決意しました。

学ぶ動機には、仕事面だけでなくご家庭での体験もあったとか。
はい。父が亡くなり、母と義母がそれぞれ一人暮らしになったんです。どちらも高齢で、介護認定も受けていて。今後のことを考えた時に、家族としても何か知識が必要だと感じました。仕事とプライベートの両面で、老年期に関する体系的な理解を深めたいと思ったのが大きな理由ですね。

学び始める前に、不安はありましたか?
もちろんありました。私は大学は経済学部出身で、老年学なんて全く縁がなかったですから。大学院は研究をする場所ですし、「研究したいテーマは何ですか?」といきなり聞かれても、そもそも老年学を知らないのにテーマなんて思いつかないんですよね(笑)。そんな状態で本当に大丈夫なのかな?とすごく不安でした。

その不安をどう乗り越えたのでしょうか?
たまたま、以前に桜美林大学大学院の老年学コースを修了された方とFacebookでつながっていて。その方に思い切って相談したんです。そしたら、「あなたの関心に合いそうな先生がいると思うよ」と言ってくださって、事前に指導教授の方とZoomで面談させてもらえることになりました。
その面談で、「研究テーマは入ってから変えても構わないし、今の時点で決まっていなくても大丈夫」と言っていただけて、すごく安心したのを覚えています。

大学院に進む決意が固まった瞬間ですね。
そうですね。それでも母たちの年齢を考えると、「今を逃したらもう学ぶチャンスはないかもしれない」と、ある種の切迫感もありました。オープンキャンパスに参加したのが入試の申し込み締切ギリギリで、迷う時間もないまま受験を決めました。

入試の準備も大変だったのでは?
ええ、研究計画書を出さなきゃいけないんですけど、正直どう書けばいいかわからなくて。でも、相談した方が「大学院初心者向けのやさしいテキストがあるよ」と教えてくださって、それを参考に2週間で書き上げました。自分の研究したいことを無理やり文章にしたような感じでしたが、なんとか提出できました。

ご家族の反応はいかがでしたか?
特に反対はされませんでしたね。どちらかというと「見守ってくれる」スタンスだったと思います。応援というより「やりたいならどうぞ」みたいな(笑)。

大学院の授業は、どんなイメージを持っていましたか?
かなり身構えていました。オンライン授業だったので、講義を受けるのは問題ないにしても、内容についていけるのか不安でした。でも、実際に始まってみたら、試験ではなくレポートでの評価が中心でしたし、自分のペースで深掘りできる科目も多くて、なんとかやっていけました。

どんな授業が印象的でしたか?
たとえば、介護保険制度の歴史や国際比較を扱った授業ですね。「なぜ日本では40歳以上から介護保険に加入するのか」といった政策の背景や、ヨーロッパ諸国との違いなどを学べたのは本当に面白かったです。
あと、心理学系の授業で「回想心理学」というものがあって。課題で「高齢の家族に過去を振り返ってもらい、人生を語ってもらう」というものがありました。私は母にインタビューしたのですが、それがすごく貴重な時間になりました。普段聞けないような話も出てきて、学びを通じて家族とのつながりも深まった気がします。

──ご自身の専門分野と重なる部分も多かったのでは?
はい。例えば年金や社会保障に関する科目は、FPとしての知識とリンクしていたので、理解しやすかったです。ただ、統計学や医学系の科目は、正直かなり苦戦しました。専門用語も多いし、授業の進度も速いので。
でも、指導教授から「全部理解しようとしなくていい。自分の研究に活かせる部分を見つけられればそれで十分」と言ってもらえて、肩の力が抜けましたね。

修士論文のテーマについて教えてください。
最終的に私が選んだテーマは、
「長期結婚継続中の夫婦における高い夫婦関係満足度の要因――妻の視点からの質的研究」
です。もともとはファイナンシャルプランナーとして、定年前後におけるお金の意思決定が夫婦間でどう行われているのかに興味がありました。でも、抽象度を上げていくと、それは「高齢期の夫婦関係満足度」につながるのでは?という指導教授のアドバイスがあり、今のテーマに落ち着きました。

研究はどのように進めていったのでしょうか?
2年目に入った1月に中間発表があり、その時点で研究計画や分析方法を明確にする必要がありました。私の研究はインタビューを用いた質的研究だったので、大学院の倫理審査を経て、ようやく調査に進めるというプロセスでした。

インタビュー相手はどうやって集めたのですか?
条件を満たす方――「結婚30年以上」「高齢(60歳〜74歳)」「健康」「夫婦2人暮らし」などを満たす妻を10名、主に知人や地元のNPOなどの紹介で探しました。ただ、テーマがかなりプライベートな内容なので、集めるのはなかなか大変でした。
最終的には10名にインタビューをお願いし、そのうち6名が条件を満たして分析対象となりました。夫婦関係満足度が「高い」と定義づけるために、チェックリスト(先行研究の尺度)を設けて事前にスコア評価していただき、その結果をもとに対象者を選びました。

夫ではなく「妻の視点」から分析された理由は?
先行研究では、高齢期において夫婦関係の満足度は「夫の方が高く、妻の方が低くなりがち」といわれています。だからこそ、「妻の視点」にフォーカスして、満足度の高い夫婦の共通点を探ってみたかったんです。

研究で見えてきたこと、気づきはありましたか?
夫婦関係満足度が高い人には、いくつかの共通項がありました。一番大きいのは「相手を尊重する姿勢」と「適度な距離感」ですね。特別に何かをしているというより、「相手の領域を侵さない」「感謝の言葉を忘れない」といった、日々の小さな積み重ねが信頼関係につながっている印象を受けました。

研究と並行して、授業や課題もあったのですよね?
はい。1年目に多くの単位を取りましたが、夜の6時40分から10時10分までの授業は本当に大変でした。特に前期は週3〜4で夜間授業があり、家で仕事をしながらの両立は相当ハードでしたね。会社勤めではなかったのでまだ柔軟に調整できましたが、体力的にはきつかったです。

学び直しで特に得られたと感じていることは何でしょう?
物事の見方がかなり変わったと思います。修士論文を書くには、必ず先行研究や一次情報に基づいた裏付けが必要です。今までは新聞やメディアの記事を読んで「そうなんだ」と思っていたことでも、「それは本当に根拠があるのか?」と考えるようになりました。
特に今はAIなどの技術も進んでいて、生成された情報に触れる機会も増えていますよね。だからこそ、「その情報の出どころは何か?」を疑う視点が、以前より鋭くなったと感じます。

FPとしての仕事にも変化がありましたか?
そうですね。高齢のお客様と話すとき、以前は想像で話していた部分が、今は学術的な知識として「こういう背景がある」と理解しながら話せるようになりました。たとえば認知症の特性や介護の制度など、専門職の連携を前提とした視点を持って対応できるようになったのは大きな変化です。

ご自身のご家族にも学びが活かされた場面はありましたか?
授業の中で「回想心理学」を学んだとき、母に人生を振り返って語ってもらうという課題が出されました。母がこれまでどんな人生を歩んできたのか、改めて聞く機会になって。なかなか普段そういう話って聞けないじゃないですか。とても貴重な時間になりました。

学び終えた今、振り返って「やって良かった」と思えますか?
はい、間違いなく良かったです。もちろん大変なことも多かったですが、それ以上に新しい世界が開けました。老年学という学問に出会えたこと、研究のプロセスを経験できたこと、それが自分の中で大きな財産になったと思っています。

最後に、「50代からの学び直し」に迷っている方へのメッセージをお願いします。
よく言われているのが、「流動性知能と結晶性知能」ってありますよね。若い頃は新しいことをどんどん覚えられる流動性知能が高いけれど、年齢を重ねると経験から学んだ知恵=結晶性知能が強くなっていく。50代以降って、まさにその結晶性知能が活きてくる時期なんです。
若い頃の「学ばされる学び」ではなく、今は「自分の意思で学びたいことを選んで学ぶ」ことができる。それって、すごく楽しいことだと思うんです。
大学院じゃなくても、講座や読書など、いろんな学び方があります。自分が心から興味を持てる分野があるなら、年齢なんて関係ない。一歩踏み出せば、思っている以上に世界は広がっているんじゃないかなと思います。

50代からの学び。
「今は自分の意思で学びたいことを選んで学ぶことができる。それって、すごく楽しいことだと思うんです」
三原ゆきさんのこの言葉とても印象的でした。
歳を重ねるほど学ぶのにはハードルが高く感じられ、体力、気力が必要と考えるものです。
それなのに、一念発起して大学院にご入学、見事修士課程を修了された三原ゆきさん、すごすぎます。
このあたりの詳しい想い、決意に関してはサロンに入っていただいて、じっくりまた講義とかで直接お話する機会も設けます。
ぜひサロンにご入会くださいね。
\豊かなセカンドライフが実現するサロン/
まずは公式LINE登録から
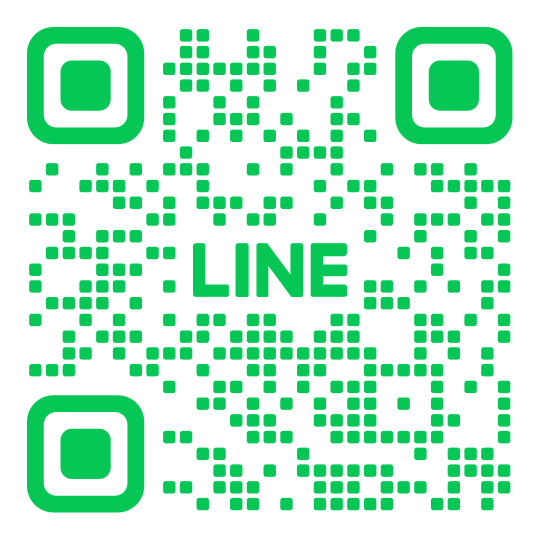
どうもありがとうございました。
