この記事は、早期退職アドバイザーのびたが主催するオンラインイベント、Xスペースの記録です。
今回は介護・社会福祉の専門家であるがんちょーさんにスピーカーになっていただいています。
イベントでは、親が認知症の可能性がある場合に家族が取るべき行動に焦点を当て、「聴くこと」「困りごとの細分化」「なんとかなっている期間の活用」という3つの重要なテーマについて詳しく解説されました。
介護保険の早期申請やかかりつけ医との連携の重要性など、予防的な対応の必要性が強調されています。
\豊かなセカンドライフが実現するサロン/
https://twitter.com/mirai_nobita/status/1970353818887168157
それではインタビューに進みましょう!
そもそも「認知症」とは病名ですか? どう捉えればいいのでしょう。
認知症は“病名”ではなく、“状態”を指します。認知症は何らかの原因疾患によって脳の機能が低下し、日常生活や社会生活に支障をきたしている「状態」を指します。
例えば、「アルツハイマー型認知症」という状態の原因疾患が「アルツハイマー病」となります。
かつては「痴呆症」や「ボケ」と呼ばれていたが、尊厳の観点から「認知症」という名称に変更されました。
しかし、名称が変わっても、世間一般の捉え方は依然として過去のネガティブなイメージを引きずっている傾向があります。
認知症のような状態を引き起こす原因疾患は70種類以上あるとされ、適切な医療機関での検査が不可欠でですね。

✨ポイント✨
1.認知症の正しい理解が重要であると指摘する。
• 病名ではなく「状態」: 認知症は特定の病名ではなく、何らかの原因疾患によって脳の機能が低下し、日常生活や社会生活に支障をきたしている「状態」を指す。例えば、「アルツハイマー型認知症」という状態の原因疾患が「アルツハイマー病」となる。
• 名称の変遷とイメージの乖離: かつては「痴呆症」や「ボケ」と呼ばれていたが、尊厳の観点から「認知症」という名称に変更された。しかし、名称が変わっても、世間一般の捉え方は依然として過去のネガティブなイメージを引きずっている傾向がある。
• 原因疾患の多様性: 認知症のような状態を引き起こす原因疾患は70種類以上あるとされ、適切な医療機関での検査が不可欠である。
2. 日本における認知症の種類日本で多く見られる認知症のタイプは以下の通りである。
• アルツハイマー型認知症: 全体の約6〜7割を占める最も多いタイプ。
• 脳血管性認知症: 脳梗塞や脳出血により脳の一部が損傷することで発症する。
• レビー小体型認知症: 全体の約4〜5%を占める。また、65歳未満で発症するケースは「若年性認知症」と呼ばれ、20代や30代で発症する事例も存在する。
3. 最新動向:MCIと治療法の進歩近年、認知症の早期発見と治療は大きく進歩している。
• MCI(軽度認知障害): 「このまま何もしなければ認知症になる可能性が高い状態」を指す。近年の検査技術の進歩により、MCI段階での発見が可能となった。65歳以上の高齢者のうち、約400万人がMCIの状態にあると推定されている。
• 早期発見の意義: MCIを早期に発見できれば、予防的な対処が可能となる。
• 新薬の開発: 最近承認された新薬の多くは、このMCIや初期の認知症患者を対象としている。これらは、アルツハイマー病の原因とされる脳内の異常なたんぱく質を早期に除去するなど、進行を遅らせることを目的としている。
• 現在の限界: 現時点では、認知症そのものを完治させる薬はまだ開発されておらず、今後の医療の発展が期待されている。
「親が認知症かな?」と思った“その瞬間”は、まず何をすべきですか?一つ目を教えてください。
まずは「聴く」ですね。「聴く」上で、親の変化に気づいた際に取るべき極めて重要な行動は、次の3つのステップです。
ステップ1 尋ねる
ステップ2 聞き直す
ステップ3 確かめる
最も重要かつこれらのステップは、本人と対話し、状況を把握するために行います。
一つずつ解説しますね。
ステップ1:尋ねる
物忘れを試すようなクイズや、疑ってかかるような態度は絶対に避けるべきNG行動です。
代わりに、本人の体調面とメンタル面の不調を丁寧に尋ねるのがお勧めです。
「最近、うちの親がこういう不安を抱えているようですが、何か思い当たることはありますか?」と尋ねることで、本人の自己認識と客観的な事実とのギャップを確認することができるのです。
周囲の人々は異変に気づいていても、家族から尋ねられるまで言い出せないケースが多いため、このアプローチは非常に有効でと思われます。
具体的には、以下の項目について尋ねて下さい。
睡眠について「夜眠れているか」「朝はいつも通り起きられているか」です。
食事につて「食欲はあるか」だけでなく、「硬いものを噛めているか」「むせることはないか」「食事内容が偏っていないか」まで深掘りしてください。
水分摂取について、高齢者はトイレの頻度を気にして水分を控える傾向があります。「何を、どのタイミングで、どのくらい飲んでいるか」を確認し、脱水や脳梗塞のリスクを伝え、水分摂取のメリットを説明してあげてください。
排泄について「便秘はないか」など、排泄に関する悩みがないか尋ねてみてください。
メンタルについて 「何か心配事はないか」を訪ねて下さい。
医療について「定期受診は行けているか」「処方された薬はきちんと飲めているか」。また、自己判断で市販薬を服用していないかも確認してあげてください。
感覚について 「視力」や「聴力」の低下は、人との交流を避ける原因となり、脳への刺激が減少するため見過ごされがちですが、非常に重要です。これも要確認ですね。
ステップ2:聞き直す
本人が訴えた不調について、さらに詳しく聞き、その内容を記録する。
記録の重要性: メモやボイスメモで本人の言葉を正確に残しておくのがいいですね。
この記録は、後日(例:3ヶ月後)の状態と比較するための重要な基準点となり、医師に病状の進行度合いを正確に伝えるための貴重な情報となります。
ステップ3:確かめる
本人の話だけではなく、周囲の人々からの情報を得てください。確認の対象は、同居家族や親しい友人、近所の人、習い事の仲間など日頃から本人と接している第三者です。

「親が認知症かな?」と思った“その瞬間”は、まず何をすべきですか?二つ目を教えてください。
二つ目は、発生している問題を冷静に分析し、誰にとっての「困り事」なのかを明確に区別することです。
本人が困っていないことは「なかったことにする」ことがだいじで、家族側の都合で問題化しないことが極めて重要なのです。
むしろ本人が困っていることは「介入のチャンス」です。本人も解決したいと思っているため、家族の話を聞き入れる可能性が高いからです。
「対峙」するのではなく、「横に座って一緒に問題を見つめる」姿勢が信頼関係を築く鍵となるので、この関係が構築できれば、無用な対立による消耗を避けられるのです。

✨ポイント✨
1.本人の困り事 vs 家族の困り事
・認知症の中核症状である「記憶障害」は、本人に自覚がなく、困っていない場合が多い。
・しかし、家族は「この間言ったでしょ」と本人を責め立ててしまいがちである。これは本人にとって困っていないことを指摘されるため、不安、羞恥心、怒りを引き起こす原因となる。
2.BPSD(行動・心理症状)への誤解
・徘徊、暴言、暴力、介護への抵抗といったBPSDは、必ずしも全員に現れる症状ではない。
・家族の間違った対応(間違いの指摘など)が、本人の「なんでこんなことを言われなければいけないのか」という当然の抵抗(SOS)を引き起こす。
・このSOSがBPSDと誤解され、結果として不必要な向精神薬などが処方されてしまう危険性がある。
3.適切な対応の原則
・本人が困っていないことは「なかったことにする」: 家族側の都合で問題化しないことが極めて重要。
・本人が困っていることは「介入のチャンス」: 本人も解決したいと思っているため、家族の話を聞き入れる可能性が高い。「対峙」するのではなく、「横に座って一緒に問題を見つめる」姿勢が信頼関係を築く鍵となる。この関係が構築できれば、無用な対立による消耗を避けられる。
「親が認知症かな?」と思った“その瞬間”は、まず何をすべきですか?三つ目を教えてください。
親がまだ自立して生活できている、大きな支障がない「なんとかなっている期間」こそ、最も重要な準備期間です。この期間を何もしないで過ごすことは、進行を手放しで見ていることに等しいと思います。
その具体的な方法として3つご紹介します。
具体的な行動 1:病院受診への同行
具体的な行動 2:介護保険の申請
具体的な行動 3:日常生活上の意識を高める
一つずつ解説しますね。
具体的な行動 1:病院受診への同行
このなんとかなっている期間に親の生活リズム、交友関係、かかりつけ医などとつながっておくことで、いざという時にピンポイントで連絡・確認が可能になります。
ハードルの低いアプローチとしては、本人を「認知症の検査」に連れて行くのは抵抗が大きいため、まずは「かかりつけ医の定期受診」に同行することをお勧めします。
このことにより、医師との連携が構築できます。診察後、本人に席を外してもらうなどして、家族が気づいた変化を医師に直接伝えれば、医師が自然な流れで専門的な検査や専門医への紹介を促してくれる可能性が高いからです。
家族が言うよりも、信頼している医師の言葉の方が本人は受け入れやすいですよね。
具体的な行動 2:介護保険の申請
介護保険は、早期申請が絶対にお勧めです。多少の支障が出始めた段階で、躊躇なく介護保険の申請を行いましょう。
そのことにより権利の確保:ができます。たとえ「自立」と判定されても決して「早すぎる」ことはありません。
もし「要支援1」や「要支援2」の認定を受ければ、介護予防サービス(デイケアでの運動、脳トレ教室など)を利用する権利を得られるのです。
また、予防の重要性もお伝えしたいことです。サービスをすぐに使う必要はないけれども、いざという時に介入できる準備を整えておくと、介護予防サービスを通じて要介護状態になるのを遅らせることができるので大きなメリットとなります。
具体的な行動 3:日常生活上の意識を高める
生活習慣の見直しも気軽にできる予防策です。食事のバランス、睡眠の質、生活リズムなどを一緒に見直しましょう。
健康であれば社会とのつながりや趣味や友人との交流など、楽しみの時間を維持・促進できるのです。

親の認知症が疑われる初期段階での対応で、その後の数年間の本人と家族のQOL(生活の質)を決定づけるそうです。
特に「なんとかなっている期間」を有効活用し、予防的なサービスや社会資源と早期に繋がることが、本人が自分らしく暮らせる時間を最大限に延ばし、家族の負担を軽減する上で決定的に重要であることに気づかされました。
何もしないで2年後に深刻な状況になってから対応を始めるケースと、初期段階で適切な対応をして進行を3年遅らせ、結果的に5年後まで穏やかな生活を維持できるケースでは、本人と家族が得られる時間と経験の価値は計り知れない、この考え方に衝撃を受けました!
がんちょーさんは、公式LINEやサロン内セミナーを通じて、より具体的な情報提供を継続そています。
また、介護職員の新たなキャリア構築支援として、自身の経験を基にした情報発信に関する有料noteも展開しているそうです。
がんちょーさんのnote→★★
このあたりの詳しい情報は、サロンに入っていただいて、じっくりまた講義などで直接お話する機会も設けます。
ぜひサロンにご検討くださいね。
\豊かなセカンドライフが実現するサロン/
まずは公式LINE登録から
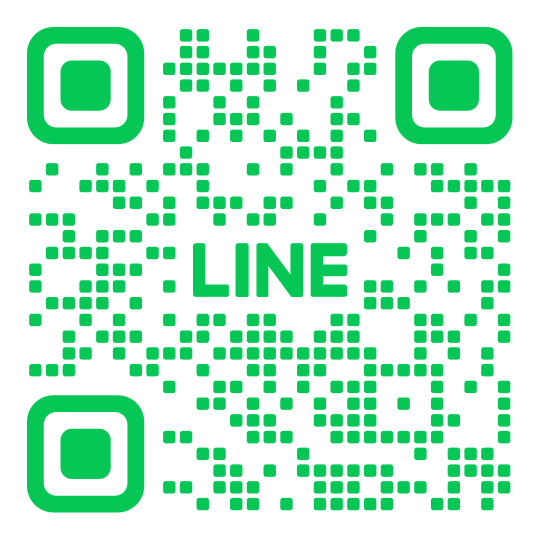
どうもありがとうございました。

どうもありがとうございました。