この記事は、早期退職アドバイザーのびたが主催するオンラインイベント、Xスペースの記録です。
\豊かなセカンドライフが実現するサロン/
それではインタビューに進みましょう!
はじめに
早期退職アドバイザーのみらいのびたです。
私が運営するオンラインサロン「早期退職研究所」は、人生100年時代を軽やかに、そして自分らしく生きるために、「お金・健康・介護」の心配から解放された人生を目指すという理念のもと活動しています。
本日は、この理念を実現する上で欠かせない「健康」の根幹をなすテーマについて、最高の専門家をお招きしました。
親子の睡眠コーチとして多くの方をサポートされている、おでこさんです。
おでこさんは、長年看護師として小児からご高齢の方まで幅広い世代の健康に携わってこられた経験をお持ちで、私たちのサロンのメンバーにとっても、非常に心強い専門家です。
今回の対談では、「明日が変わる!睡眠の専門家が教える快眠のメカニズムと最新の基礎知識」と題し、私たちが毎日当たり前のように行っている「睡眠」について、その本質から実践的なテクニックまで、深く掘り下げていきます。
この対談を通じて、皆様の毎日がより健康的で活力に満ちたものになるヒントをお届けできれば幸いです。
1. 専門家への道:睡眠科学への探求の始まり
「睡眠を削って頑張る」。
多くの現代人にとって、それは半ば当たり前の習慣かもしれません。
しかし、その先に待っているのが心身の崩壊だとしたら…?
睡眠の専門家であるおでこさんがこの道に進んだ背景には、まさに仕事と子育ての両立の中で経験した、壮絶な原体験がありました。

元々は保育園の看護師をされていたおでこさんが、なぜ「睡眠」というテーマについて、これほど深く学び始めようと思ったのでしょうか?
そのきっかけを教えてください。
仕事と子育てを両立させる毎日は、本当にギリギリの連続で。日々のタスクをこなすために、私は当たり前のように睡眠時間を削って活動していたのです。
しかし、そんな生活が長く続くはずもなく、ある日、ついに体調を崩してバタッと倒れてしまいました。
その時、「うわあ、これはまずいな」と思いながらも、とにかくひたすら寝てみたんです。
すると、自分でも驚くほどすっごい回復したんですよ。
この経験を通して、「ああ、眠ることはこんなにも大切なことだったんだ」と、身をもって痛感したのです。
加えて、当時保育園の看護師として働く中で、子どもたちの睡眠にも大きな課題があると感じていました。
これらの経験が重なり、「誰もが毎日行っているけれど、意外と軽視されがちな『睡眠』について、もっと深く知りたい」という興味が湧き、専門的に学ぶ道へと進むことになりました。
今では、オタクと言われるレベルで睡眠の世界を探求しています。

突き詰めれば突き詰めるほど面白いとのことですが、おでこさんが感じる睡眠の「面白さ」とは、具体的にどのような点にあるのでしょうか?
一つは、その多様性と個別性です。私たちの毎日は一日として同じ日はありません。
それと同じように、睡眠も一夜として全く同じものはなく、その日の活動や体調によって常に変化します。
さらに、人それぞれの体質や生活習慣によっても最適な睡眠は異なります。
だからこそ、「これをやれば絶対にこうなる」という単純な正解はなく、常に「トライアンドエラー」を繰り返しながら自分にとっての最適解を探していく奥深さがあります。
そしてもう一つは、確実なリターンがあることです。
様々な要因で変化する一方で、適切に質の良い睡眠をとることができれば、翌日には必ず心と体が元気になるという、明確な見返りが得られます。
努力すればするだけ、何かしらの良い結果として自分に返ってくる。この手応えも、睡眠を探求する上での大きな魅力だと感じています。

なるほど。
なんだか、X(旧Twitter)の投稿みたいですね。
日々トライアンドエラーを繰り返して、反応も毎日違う。
でも、ちゃんと根拠のある良い投稿をすれば、「いいね」がもらえたり、バズってフォロワーさんが増えたりして「元気になる」というリターンが返ってくる。
そう考えると、まったく同じかもしれません(笑)。
面白いです。

ご自身の壮絶な体験から回復までの道のりは、非常に説得力がありますね。
睡眠を単なる「休息」ではなく、人生を好転させるための「ツール」として捉え直すきっかけになりました。
そのツールを効果的に使いこなすためにも、まずはその設計図、つまり睡眠とは一体何なのか、基本的な科学から教えていただけますか?

2. 睡眠の正体:その定義と驚くべき役割
人生の約3分の1を費やす「睡眠」。
しかし、その正体について「なぜ眠くなるのか」という根源的な問いには、現代科学でさえ明確な答えを出せていません。
当たり前すぎて意識することのなかったこの生命活動には、一体どのような定義があり、私たちの心身にどんな驚くべき役割を果たしているのでしょうか。

それでは、基本的なところからお伺いします。「睡眠」とは、科学的にどのように定義され、どのようなメカニズムで成り立っているのでしょうか?
しかし、現時点で分かっていることから、「睡眠」の状態を定義することはできます。
科学的には、以下の4つの条件を満たした状態を「睡眠」と判断します。

- ① 睡眠と覚醒を行き来できる(可逆的である)
- 意識を失っている昏睡状態とは異なり、いつでも目覚めることができる状態です。
- ② 行動が停止し、特徴的な姿勢をとる
- 活動が止まり、休息のための姿勢をとります(人間が横になったり、鳥が枝に止まったりするような、種に特有の姿勢)。
- ③ 外部からの刺激に対する反応が鈍くなる
- 物音や呼びかけなど、周囲の刺激に気づきにくくなります。
- ④ 睡眠不足が続くと、その後より長く深く眠る
- 睡眠が不足すると、体はそれを補おうとする働き(睡眠負債の返済)をします。
非常に明確な定義があるのですね。
では、その睡眠中、私たちの体や脳の中では具体的にどのようなことが行われているのでしょうか?
特に、以前お聞きした「脳のお掃除」という機能について、詳しく知りたいです。
日中の活動で疲弊した心と体を修復し、翌日のパフォーマンスを最大化するための、非常にアクティブなメンテナンス時間です。
その役割は、大きく「身体」と「脳・心」への機能に分けられます。

- 体の回復:
日中の活動で溜まった疲労物質を取り除き、筋肉や組織を修復します。 - 見た目を整える:
成長ホルモンが分泌され、肌のターンオーバーを促進したり、脂肪の代謝を促したりします。 - 免疫系の強化:
免疫細胞が活性化し、病原体と戦う力を高め、病気にかかりにくい体を作ります。 - 代謝の調節:
血糖値やホルモンバランスを正常に保ち、生活習慣病のリスクを低減させます。 - 脳のメンテナンス(お掃除):
睡眠中に最も重要な役割の一つです。脳内では**「グリンパティックシステム」という仕組みが活発に働き、脳細胞の間に溜まった老廃物を洗い流します。この老廃物には、アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドベータなども含まれており、睡眠による脳の清掃は、将来的な認知症リスクの軽減にも繋がると考えられています。この老廃物がわずか1〜2日溜まるだけでも、幸福感が低下したり、頭にモヤがかかったような思考力の低下を招いたりします。 - 認知機能の向上:
脳をリフレッシュさせ、学習能力、判断力、集中力を高めます。 - 記憶の定着:
日中に得た膨大な情報を整理し、重要なものを長期記憶として脳に定着させます。 - 精神的な安定:
感情を司る脳の領域を整え、ストレスを緩和し、心を穏やかに保ちます。寝不足だとイライラしやすくなるのは、この機能が低下するためです。
睡眠が、日中のパフォーマンスを最大化し、長期的な健康を守るための、極めて積極的なメンテナンス活動であることがよく分かりました。
これだけの恩恵があるということは、裏を返せば、それを放棄することのリスクも相当なものだと想像します。
もし眠らなかったら、私たちの心身にはどのような危険が待ち受けているのでしょうか?
私たちは徹夜明けを「辛い一日」の始まりくらいに考えがちです。
しかし、その代償がもし、人間の精神そのものの崩壊だとしたら…?
11日間眠らなかった男性を医学的な観察下で記録した衝撃的な実話は、睡眠不足が単なる疲労の問題ではなく、心と体が壊れていく恐ろしい旅路であることを明らかにします。

これほど多くの重要な役割を担っている睡眠を取らない状態を続けると、私たちの身体や心には、具体的にどのような危険が及ぶのでしょうか?
それは、「11日間眠らなかった」というギネス記録です。この挑戦は、命に関わるほど極めて危険な行為であるため、現在ではギネス協会も認定を取りやめています。
当時、アメリカの若者が挑戦したこの不眠実験では、時間の経過とともに彼の心身に恐ろしい変化が現れました。

- 2日目: 怒りっぽくなり、集中力が著しく低下。
- 3日目: 吐き気を催すようになる。
- 4日目: 存在しないものが見える妄想が出現。本人は強い疲労感を訴える。
- 5日目以降: 症状はさらに悪化。記憶が欠落し始め(6日目)、視覚に異常をきたし(7日目)、体が震え、ろれつが回らなくなるなどの言語障害が発生。最終的には会話そのものが成立しなくなっていきました(9日目以降)。

壮絶な記録ですね。
それほどまでに睡眠は生命維持に不可欠なのですね。しかし、現代社会にはスマートフォンや仕事など、睡眠を妨げる誘惑や要因が多すぎると感じます。
私たちは、この状況にどう向き合えばよいのでしょうか?
4.現代社会と睡眠:なぜ私たちは眠れないのか
睡眠の重要性を頭では理解していても、現代社会で十分な睡眠を確保することはなぜこれほど難しいのでしょうか。
その背景には、個人の意思だけでは抗いがたい社会構造や、「寝ずに頑張ること」を美徳としてきた文化的な刷り込みが深く根付いています。
ここでは、私たちが眠れなくなっている根本原因を解き明かします。

スマートフォンの誘惑、終わらない仕事、育児の負担など、現代人の周りには睡眠を妨げる要因が溢れています。
このような環境の中で、私たちはどうすれば良質な睡眠を確保できるのでしょうか?
この状況を乗り越えるために最も重要なのは、睡眠に対する根本的な「意識改革」だと私は考えています。
まず、日本人は世界的に見ても睡眠時間が極端に短いという事実があります。
OECD(経済協力開発機構)の調査では、加盟国の中でワースト1位です。この背景には、日本特有の文化的な要因が根強く存在します。
バブル期の「24時間戦えますか」というキャッチコピーに象徴されるように、日本では「寝ずに働くこと」が美徳とされる風潮がありました。
また、「母さんが夜なべをして…」といった童謡からもわかるように、夜更かしして何かに励む姿が美しいこととして、無意識のうちにすり込まれています。
しかし、近年は「頑張るために夜更かしする」のとは少し違う、新たな問題が深刻化しています。
それが「リベンジ夜ふかし」という現象です。日中のストレスを発散させるため、夜に自分の時間を確保しようとスマホに没頭してしまうのですが、これは罠です。
SNSや動画は、脳内で快楽物質であるドーパミンを放出し続けるように設計されており、脳をリラックスさせるどころか、逆に興奮させて眠りから遠ざけてしまうのです。
このように、私たちの周りには睡眠を削る要因が満ち溢れています。
だからこそ、私たちは睡眠を「余った時間でするもの」ではなく、「意図的に確保するもの」へと意識を変え、社会の風潮や誘惑に「抗う勇気」を持つことが不可欠なのです。

なるほど、文化的な背景から最新のテクノロジーまで、様々な要因が複雑に絡み合っているのですね。
その「意識改革」を具体的に行動に移すためには、どのようなことから始めればよいのでしょうか?
5. 実践・快眠メソッド:明日からできる質を高める習慣
質の高い睡眠は、夜の過ごし方だけで決まるわけではありません。実は、朝起きた瞬間から夜の眠りの質を高めるための準備は始まっています。
ここでは科学的根拠に基づき、明日からすぐに実践できる具体的な習慣を、朝・昼・夜の時間軸に沿ってご紹介。最高の眠りをデザインするための、1日の設計図です。

睡眠の質を決定づける重要な要素は何でしょうか?
特に、眠り始めにあるという「黄金の90分」を確実に確保するためには、具体的にどのようなことを実践すれば良いのか、その方法を教えてください。
睡眠の質は、眠り始めてから最初に訪れる最も深いノンレム睡眠、いわゆる**「黄金の90分」でその大部分が決まります。
この時間帯に成長ホルモンが最も多く分泌され、心身の回復が効率的に行われます。
この「黄金の90分」をいかに深く、質の高いものにするかが快眠の鍵となります。
そのための具体的な習慣を、朝・昼・夜に分けてご紹介します。

- 太陽光を浴びる
起床後すぐにカーテンを開け、太陽の光を浴びましょう。光が目に入ることで体内時計がリセットされ、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが分泌されます。このセロトニンは、約14~16時間後に、自然な眠りを誘う睡眠ホルモンであるメラトニンに変化します。つまり、朝の光が夜の眠気を作り出すのです。 - リズム運動と朝食
ウォーキングなどの一定のリズムを刻む運動や、朝食をよく噛んで食べることもセロトニンの分泌を促します。特に朝食では、セロトニンの材料となるトリプトファンが豊富なタンパク質(卵、大豆製品、乳製品など)を意識的に摂ると効果的です。
現代人はデスクワークが多く、脳ばかりが疲れて体は疲れていない、というアンバランスな状態に陥りがちです。
この状態では、夜になっても頭が冴えてしまい、寝付けない原因になります。
日中にウォーキングや軽い運動など、心地よい身体的疲労感を得られる「アクティブレスト」を取り入れ、脳と体の疲労バランスを整えることが重要です。
- 照明を落とす 日が落ちたら、部屋の照明を落としましょう。蛍光灯のような白い強い光は脳を覚醒させてしまいます。暖色系の間接照明などを使い、心と体がリラックスできる薄暗い環境を作るのが理想です。
- 食事は就寝3時間前までに 就寝直前に食事を摂ると、消化活動のために内臓が働き続け、眠りが浅くなります。理想は就寝の3時間前までに済ませること。難しい場合は、夕方におにぎりなどを食べ、帰宅後はスープやサラダで軽く済ませる「分食」などの工夫も有効です。
- 入浴で深部体温をコントロールする 就寝の90分前を目安に、40℃前後のお湯に15分程度浸かりましょう。これにより、体の中心部の温度である「深部体温」が一旦上昇します。そして、この上がった深部体温が下がっていく過程で、人は強い眠気を感じるようにできています。このように、意図的に深部体温を一度上げ、その後の自然な体温低下を利用することが、自分でコントロールできる強力な眠りのスイッチになるのです。
朝から夜までの過ごし方全てが、夜の眠りに繋がっているのですね。非常に勉強になります。
ところで、私のサロンのメンバーはシニア世代の方が多いのですが、年齢を重ねた場合の睡眠について、何か特別なアドバイスはありますか?
6. シニア世代の睡眠戦略:変化を受け入れ、質を高める
年齢を重ねるとともに「眠りが浅くなった」「朝早く目が覚めてしまう」といった変化を感じるのは、ごく自然なことです。
しかし、それは「老化」ではなく、変化するライフステージに身体が適応していく「進化」と捉えることができます。
ここでは、シニア世代が自身の睡眠の変化と前向きに付き合い、時間よりも質を高めていくための心構えと戦略をお伝えします。

私自身も、若い頃に比べて「眠りが浅くなった」と感じることがあります。
シニア世代が直面しがちな睡眠の課題と、それに対する具体的な対策について教えていただけますでしょうか。
この変化を悲観的に捉えるのではなく、前向きに受け入れることが、質の高い睡眠への第一歩です。
その上で、以下の3つのポイントを意識してみてください。

- ① 過度な心配は禁物。「大らかに構える」姿勢が大切
「眠れない」という事実に対して過度に悩み、不安を感じてしまうと、そのストレスがかえって脳を覚醒させ、ますます眠れなくなるという悪循環に陥りがちです。「まあ、1日ぐらい眠れなくても、人間って意外と大丈夫なものだ」と、大らかに構えることが何よりも大切です。 - ② 時間よりも「質」の向上に注力する
加齢によって睡眠時間が短くなるのは自然なことです。だからこそ、これまでお話ししてきた快眠メソッド(朝の光、入浴、照明の工夫など)を実践し、眠っている時間の「質」を最大限に高める努力がより重要になります。 - ③ 完璧を目指さず、緩やかに実践する
全てのメソッドを完璧にこなそうとすると、それが新たなストレスになりかねません。大切なのは、無理なく続けられること。「まずは朝の光を浴びることから試してみよう」というように、まずは一つから試してみるという緩やかな姿勢で、楽しみながら改善していくことをお勧めします。
6.おわりに
本日は、睡眠の専門家であるおでこさんをお招きし、人生の3分の1を占める「睡眠」について、そのメカニズムから実践的な改善法まで、多岐にわたる貴重なお話を伺いました。おでこさん、本当にありがとうございました。
睡眠が単なる休息ではなく、日中の活動を支え、心身の健康を維持するための積極的なメンテナンス活動であることを改めて深く理解することができました。
さて、今回のお話を聞いて、さらに睡眠について学びたいと思われた方も多いのではないでしょうか。おでこさんとは、今後もさらに深いテーマでイベントを開催する予定です。
- 公式LINE限定ミニ講座(11月4日 13:00〜)
- 「50代からの新常識、あなたの眠りは進化している!世代別快眠シフトチェンジ術」
- サロンメンバー限定講座(11月14日 13:00〜)
- 「人生100年時代の睡眠戦略!50代が目指すべき理想の睡眠リズム確立メソッド」
ご興味のある方は、ぜひ私の公式LINEにご登録ください。
また、おでこさんは本日お話しいただいた内容以外にも、様々なメディアで睡眠に関する有益な情報を発信されています。ぜひフォローして、日々の生活にお役立てください。
今日学んだことを一つでも実践することで、あなたの明日はきっと変わります。ぜひ、意識改革の第一歩を踏み出してみてください。本日はご参加いただき、誠にありがとうございました。
\豊かなセカンドライフが実現するサロン/
まずは公式LINE登録から
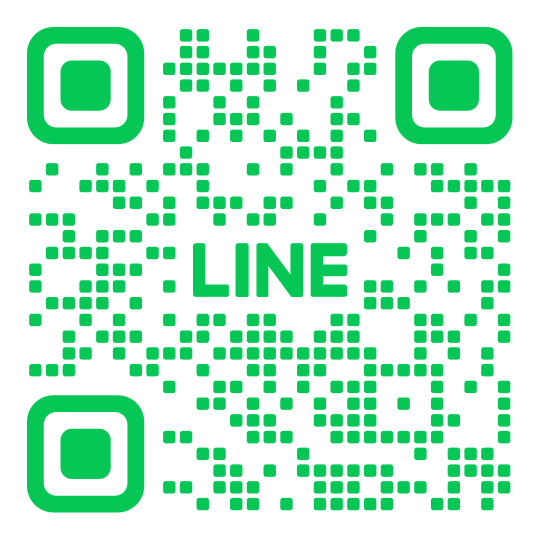

どうもありがとうございました。